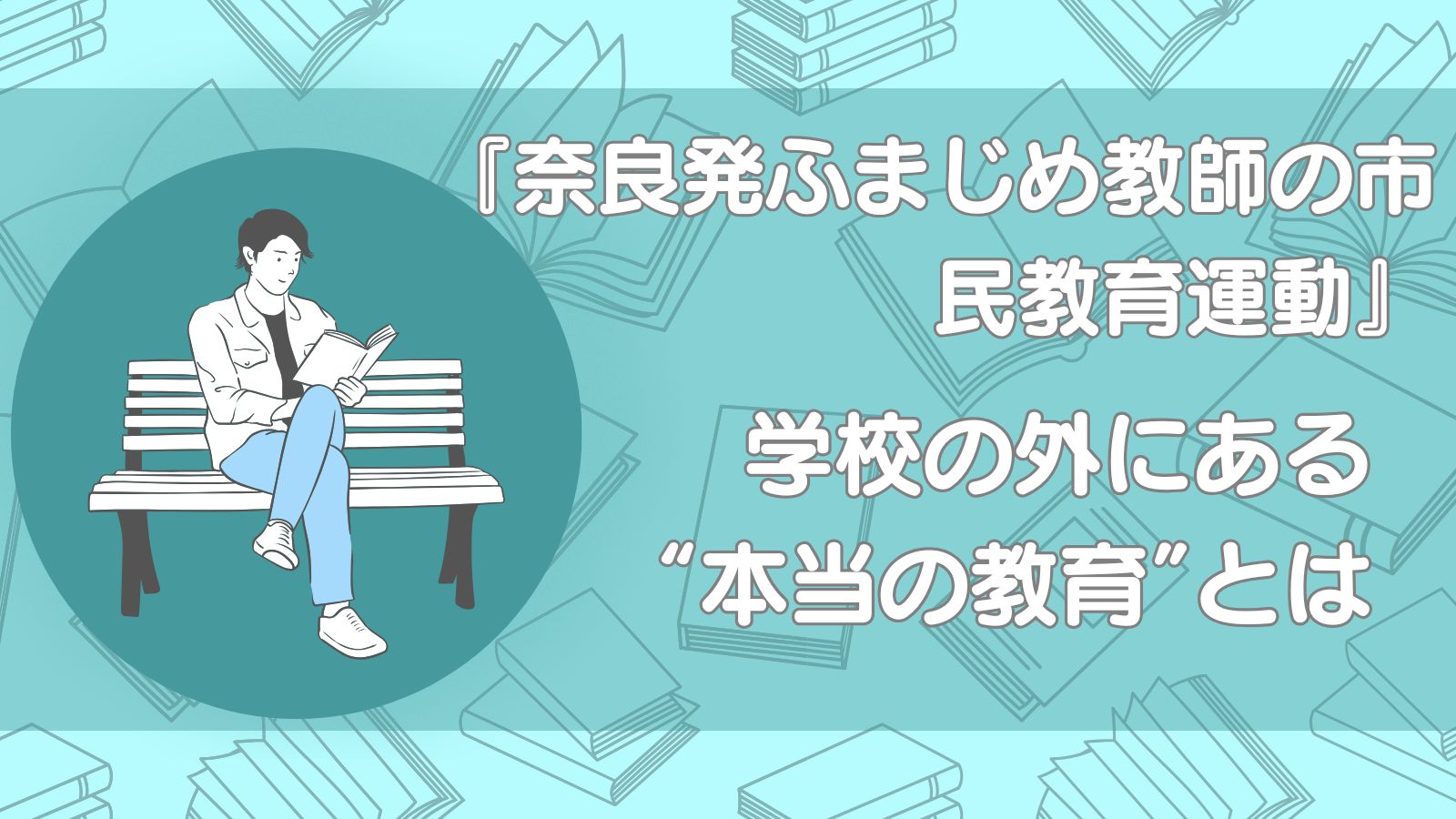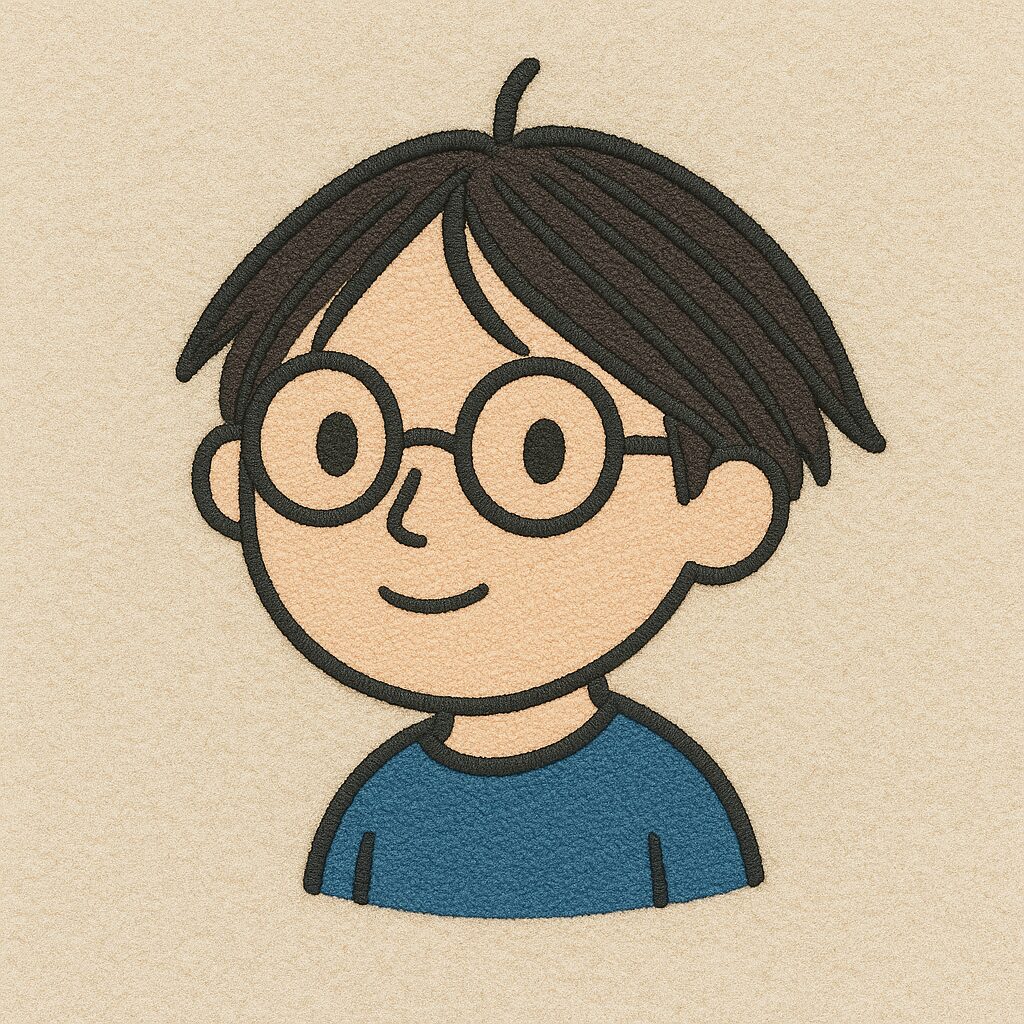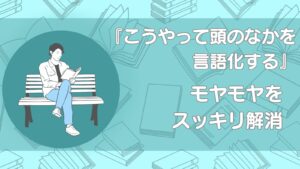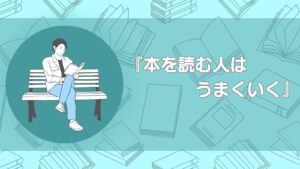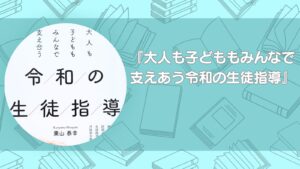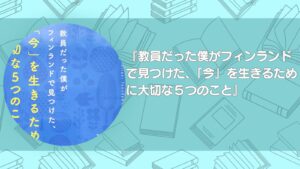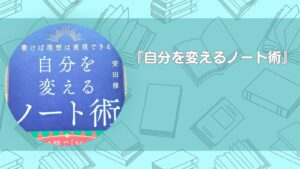教育現場で働く人や、子どもの成長過程で悩む親にとって、
「学校という環境で行われる教育がいいのか?」そんな疑問をもちました。
「学校の外にも教育」があるのか?その問いの答えがこの本でした🥺
この本は、著者自身の教師としての歩みを軸に、学校という枠を超えた“教育のかたち”を問い直す内容です。
この本を読むことで見えてきたのは、次のようなテーマでした。
子どもたちの背景にある「見えない困難」
学校には、さまざまな生活背景をもった子どもたちが集まります。
近年では、国籍や文化が異なる子も増え、教室がより多様な空間になっています。
それ自体はとても良いことです。人は互いに支え合いながら生活している存在だからです。
しかし一方で、外見からは分からない「見えない困難」を抱える子も少なくありません😥
たとえば、経済的な理由で塾に通えない子ども、
家庭の事情で安心できる居場所を持てない子、
日本語の読み書きに不自由を感じる子など――。
これらは個人の努力だけではどうにもならない、
“社会の仕組みからこぼれ落ちた”問題でもあります。
著書は、まさにこうした子どもたちと向き合いながら、
「学校の外にもう一つの教育の場をつくる」取り組みを続けてきました。
本の要点・構成の紹介
この本は、著者の教育人生において学んだこと、気づいたことが書かれています。
さらに現代教育のあり方に鋭い問題提起を投げかけています。
構成は以下のように展開されています。
どの章からも、「教育とは、人と人が出会い、支え合う営みである」というメッセージが伝わってきます。
見えない困難に向き合う教師の姿
💡「教師=まじめ」からの脱却
教師という職業は、多くの人が「真面目」「間違ってはいけない」というイメージを抱いています。
しかし、著者はその“型”を一度疑ってみることの大切さを教えてくれます。
むしろ柔軟で、時に“ふまじめ”であってもいい。
失敗や迷いを通して人間らしさを見せることで、子どもたちも安心して自分を出せるようになります。
この姿勢こそが「人に寄り添う教育」なのだと感じました。
💡学校外の教育拠点をつくるという発想
「市民ひろばなら小草」や「すみれ塾」は、学校外に学びの居場所をつくる活動です。
そこでは、不登校や貧困など、さまざまな事情で学校に馴染めない子どもたちが集まっています。
💡多文化共生=ともに学ぶ教育の姿勢
文化交流ができる場所として「シャオツァオ」という活動をしています。さまざまな国籍の子どもや家庭が地域と関わりながら学んでいます。
言葉は単なるコミュニケーション手段ではなく、その国の文化や歴史が詰まった“生きた学び”です。
親が子に文化や言葉を伝えるように、教育もまた次の世代へと受け継がれていく。
この視点をもつことで、「違い」から学び合う社会をつくる第一歩が見えてきます。
市民教育運動から学ぶ、地域とつながる教育のかたち
💡教育は「学校」だけで完結するものではない
この一文に、本書のメッセージが凝縮されています。
現場で働く教師の声が届きにくくなっている今、
「市民教育運動」は、教育の“セーフティネット”であり“希望の場”でもあります。
💡著者の「命こそ宝」という言葉には、
肩書や立場を超えた“人としての眼差し”が込められています。
生きていれば、困難もあるけれど、誰かが支えてくれる──
そんな人間の強さと優しさを思い出させてくれました。
私自身も、「正しさ」だけにとらわれず、
真実を見つめ、人の心に寄り添う柔軟さを大切にしていきたいと思いました。
教育現場で生かせる3つの気づきと行動のヒント
この本を通して、公教育の背景、現代教育の形がみえてきました。
公教育はたくさんの声を拾っていると思います。
どうしても拾えない「小さな声」を気づく大切さを学びました。
これから意識したい行動は次の3つです。
・小さな違和感を見逃さず「助けが必要な人」に声をかけたい
・今を生きている私たちは、先人達の頑張りの上でなっているので、次世代につなげたい
・地域や仲間と協力し、誰もが学びやすい社会を育てる
教育とは“教える”ことではなく、“つながりを紡ぐ”こと。
この本を読み、そんな原点に立ち返るきっかけをもらいました。
まとめ:教育の未来を支える私たちへ
『奈良発ふまじめ教師の市民教育運動』は、長年教育現場で働いてきた著者による、
「教師の視点から社会に問いかける」一冊です。
特におすすめしたいのは次のような人たち。
・教育に「理想」と「現実」のギャップを感じて新しい教育を探している先生
・不登校や格差の問題に向き合い、子どもの居場所を考えたい親世代
・子どもを支えたいと思うすべての人
『奈良発ふまじめ教師の市民教育運動』は、
“まじめさ”の殻を破り、もう一度「教育とは何か」を問い直すきっかけをくれる本です。
学校の外にこそ、本当の教育の現場がある──そんな気づきを得られる一冊でした。