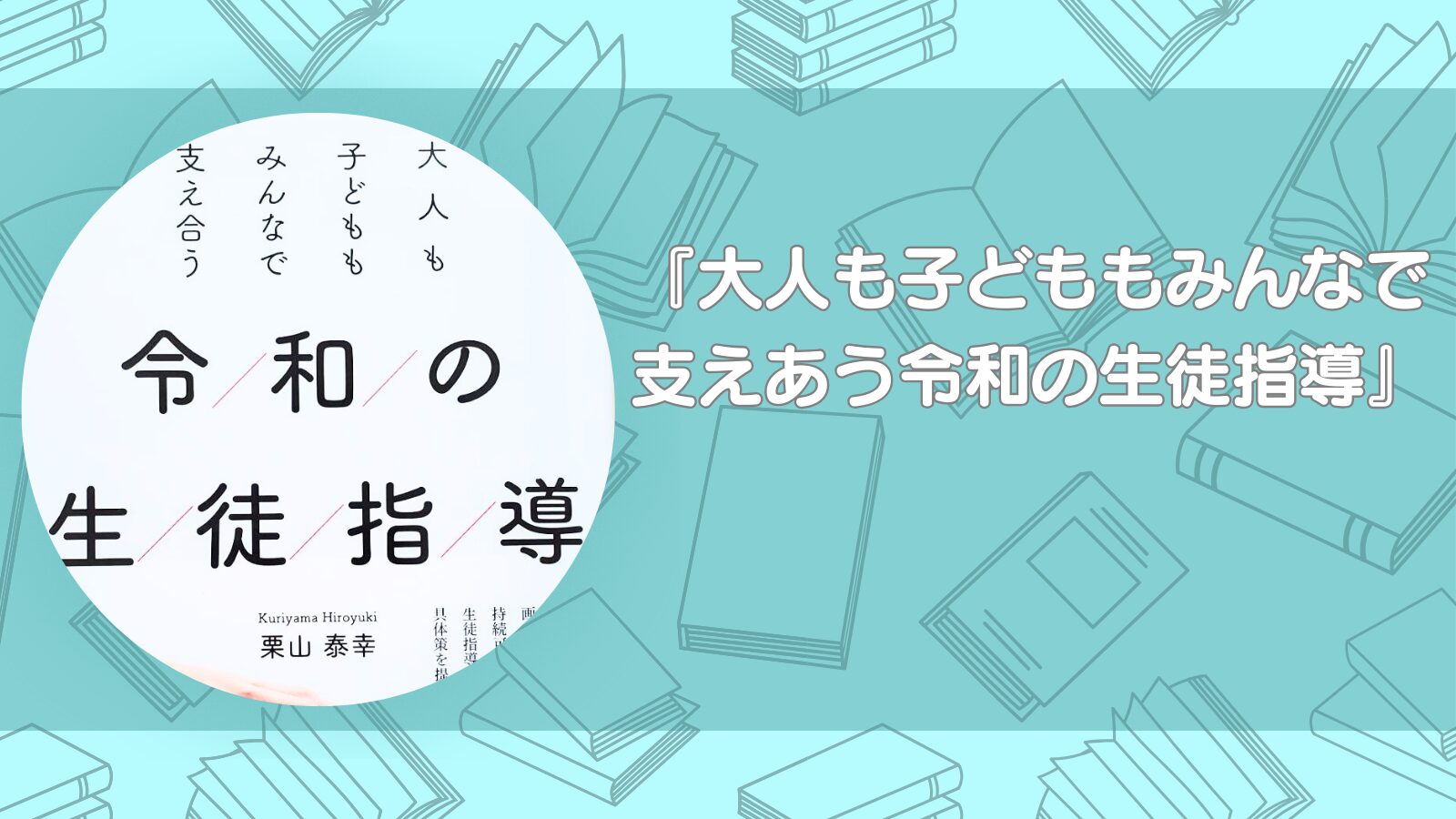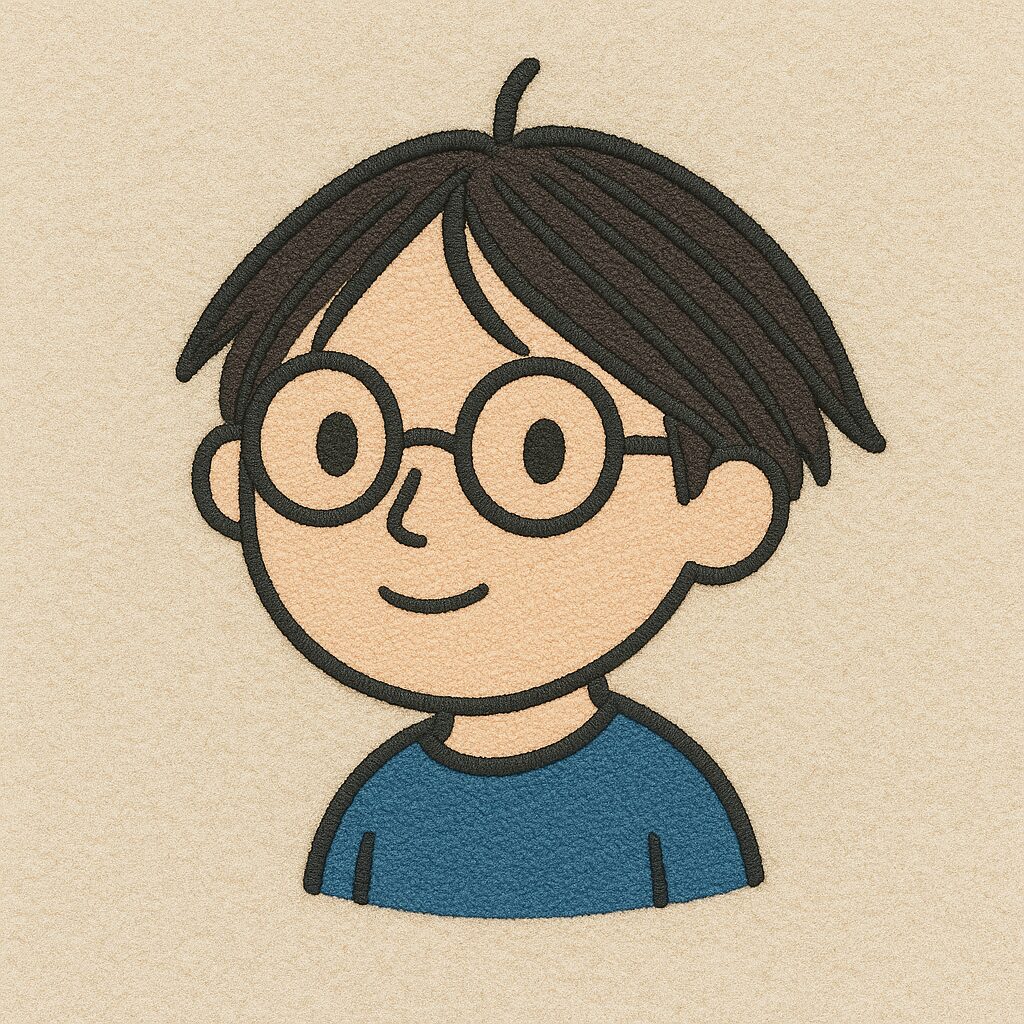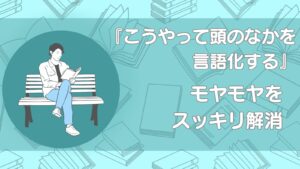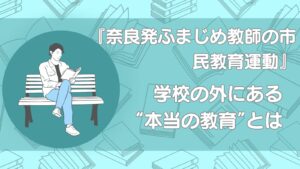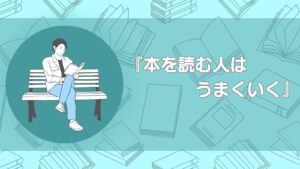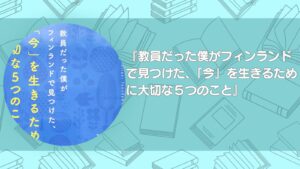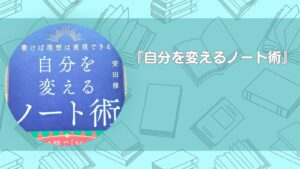生徒指導とは、決して「問題を正す」ことだけではありません。
その根底にあるのは「信頼関係」であり、子ども一人ひとりと丁寧に向き合う姿勢です。
この本には、そんな人と人との関係性を大切にする視点が詰まっています✨
現役教員はもちろん、保護者や教育、子ども達に関わるすべての人に、ぜひ読んでほしい一冊です📘
はじめに:この本を読んだ理由
子どもとの関わりに悩んでいたとき、手に取った一冊です📖
「どうしたら信頼関係を築いて、子どもたちが安心して過ごせる日常にできるか」
迷っていた私に、この本は優しく寄り添い、たくさんのヒントを与えてくれました🌱
本の特徴
この本は、テクニックやハウツーではありません。
「令和の時代に、人と人が心地よく過ごすにはどうすればよいか」
その問いに向き合いながら、教育現場に寄り添った内容が語られています✨
構成は以下のようにシンプル‼️でも深い学びがあります☺️👍
序章:現場の現状と信頼関係の重要性
今、学校現場で何が起きているのか。その背景と課題が整理されています。
第1章:生徒指導のマインドセット
子どもにどう向き合うか。「まず聴く」「共にいる」という姿勢の大切さを学びます。
第2章:生徒指導の基本スキル
心理的な視点を交え、現場ですぐに実践できる関わり方が紹介されています。
第3章:チームで支える学校づくり
ひとりで抱え込まない仕組みをどうつくるか。職場の教員、保護者、子ども達との連携と信頼がカギになります。
第4章:全員が主体の授業づくり
大人も子どもも学び合う、関係性のある日常の授業姿が描かれています。
終章:学び続ける覚悟
誰も失わないために。著者の学び続ける姿勢が、読者にも問いかけてきます🌱
読んで変わる行動のヒント

生徒指導は“チーム”で行うもの
生徒指導において、孤立しながら奮闘する先生は少なくありません。
けれど著者は「一人で抱えなくていい」と語ります。
保護者や同僚、さらには子どもたちとも連携し、“チーム”で支えることが大切なのです🧑🤝🧑
たとえば、問題行動があったとき、大人同士が信頼し合い連携を取ることで、子どもに安心感が生まれますね。
大人にも得意・不得意がありますが、バラバラな指導では子どもは混乱してしまいます💦
だからこそ、学校も家庭も「支え合う関係」を築くことが出発点です🌈
さらに著者は子ども達の力を信じていることです。
この本には子ども達の目線にたった内容が数多く書かれています。
特に注目すべき取組みが「美点凝視」です。📷
美点凝視とは子どもの成長や良さを写真に収め、励ましのメッセージを添えてポスターとして掲示する取り組みです。
このように学校全体で子どもを肯定的に見つめる姿勢が、大切にされています✨
詳しい内容は本書に紹介されています。
著者は学校に関わる全員でチームになろうと取組んでいます。
「わからないことが増えた」という覚悟ある学び
著者の印象的な言葉に「学び続けても、わからないことが増えてきた」があります。
これは教員歴20年以上の著者が、自らの経験と葛藤から実感として語っている言葉ですね🔍
公認心理師、臨床発達心理士の資格を取得し、現在は名古屋大学の博士課程で学びを深める著者。
その肩書き以上に、「今もなお学び続けている」その姿勢に強い覚悟を感じています。 子どもたちと向き合う想いが伝わってきますね。
正解を押しつけるのではなく、「一緒に考えよう」と向き合う姿勢こそが、生徒指導の原点だと感じました🌱
テクニックじゃない。「心地よく生きる」を一緒に考える本
本書はルールや技術ではなく、1人1人に向き合い「どう関わるか」「どう生きるか」といった本質に迫る一冊ですね。
規則や校則といった行動指針ではなく、「あなたはどうしたい?」「私はどう感じている?」
そんな対話から始まる関係づくりが描かれています💬
読み終えたあと、著者ともっと語り合いたくなるような本書になります。
まるで対話しているように読み進められる、不思議なあたたかさを感じました☺️
心に残ったメッセージ3選

「……そして、もう誰一人失いたくないです。そのために少しでもできることがあればいくらでも学び続けたいです。」
‐大人も子どももみんなで支えあう令和の生徒指導 P.201
子どもたちの命と心に真剣に向き合う、覚悟ある言葉に胸を打たれました🕊️
「……引っ張っていけるほどの力を自分がつけたとは思えません。ますます自分がわかっていないことがたくさんあることがわかりました。……」
‐大人も子どももみんなで支えあう令和の生徒指導 P.200
学びには終わりがない。謙虚さを忘れず、新しい扉を開いたら次の扉へと、問い続ける姿勢に感動しています🌿
「自分がよく理解できない相手に、それらしいラベルを勝手に貼りつけて、理解した気になりたい人がいるのです。」
‐大人も子どももみんなで支えあう令和の生徒指導 P.170
人は一側面だけで語れない。理解しようとする姿勢を持ち続けることが大切だと学びました🔍
読んで変わったこと
この本を読んで、子どもとの関係づくりやチーム構築についての考え方が大きく変わりました✨
信頼は一朝一夕では築けません。だからこそ、まずは目の前の子どもをしっかり見つめることから始めたいですね。
そして職場環境も、誰かの犠牲で成り立たせるのではなく、協力と尊重のある場所へと改善していこうと思いました🛠️
まとめ:こんな人におすすめ
- 子どもとの関係に悩んでいる現役教員や保護者
- 学校現場で「信頼関係」や「職場改善」にヒントを得たい人
- 子どもに関わるすべての大人たち
読んで終わりではなく、行動に移したくなる優しさと覚悟が詰まった一冊です📘
生徒指導は決して先生ひとりで行うものではありません。
保護者や同僚、そして子どもたちと“チーム”で支え合うことが、教育の未来を明るく照らしてくれます🌈
やさしい言葉と実践に裏打ちされた学びから、あなたにもきっと気づきがあるはずですよ‼️
子ども達に関わるすべての人に、ぜひ手に取ってほしい一冊です📚